★ ファッション・デザイナー編① ★ 「アルマーニ」(2004年発表)
日常生活そのものが私の仕事である
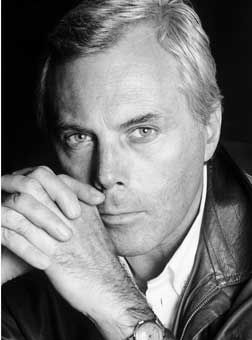 ご存知ファッション・デザイナーの大御所ジョルジュ・アルマーニの、世界を飛び回る1年間の行動を編集したドキュメンタリーじゃ。 2000年夏のミラノ・コレクションに出品する服のデザインから、モデルのウォーキング、時間配分まで細かく指示を出すアルマーニ。 同年秋に開店するパリの新店舗づくりにおいて、足繫く通いながら建築資材まで入念にチェックするアルマーニ。 ニューヨーク・グッゲンハイム美術館において、自身の個展という新しい企画に対して激しく思案するアルマーニ。 さらにスタッフとの離れ小島での余暇の様子などを含めて、多忙を極めるアルマーニの姿が活写されておる。 ご存知ファッション・デザイナーの大御所ジョルジュ・アルマーニの、世界を飛び回る1年間の行動を編集したドキュメンタリーじゃ。 2000年夏のミラノ・コレクションに出品する服のデザインから、モデルのウォーキング、時間配分まで細かく指示を出すアルマーニ。 同年秋に開店するパリの新店舗づくりにおいて、足繫く通いながら建築資材まで入念にチェックするアルマーニ。 ニューヨーク・グッゲンハイム美術館において、自身の個展という新しい企画に対して激しく思案するアルマーニ。 さらにスタッフとの離れ小島での余暇の様子などを含めて、多忙を極めるアルマーニの姿が活写されておる。
アルマーニの有名な発言に「仕事を捨てることは、人生を捨てることだ」ってのがあるが、余暇を楽しむ姿までアルマーニは超真剣であり、全編にわたって観る側にも真剣さを求められるようなドキュメンタリーじゃよ。
個人的に非常におもしろかったのは、ミラノ・コレクションの準備模様や当日の楽屋風景。アルマーニが「何故指示通りにやってないんだ!」と怒りまくり、瞬時にあらためて的確な指示を出すシーンの数々。 モデルさんもスタイリストさんも照明係さんもショーマスターさんもみんなビビりまくりなのに、まさにアルマーニの「鶴の一声」で状況が魔法のように改善されていくのじゃ。
撮影しているカメラさんまでが現場の殺伐とした雰囲気に動揺していたようで、途中画像が乱れたりするものの、それも却って現場のリアリティが伝わってくる! 乱れるのはカメラさんだけではなくて、お美しいモデルさんが極限の緊張のあまりついつ い着替えるタイミングを間違ったのか、カメラの前でおっぱいポロリ!なんて場面もそのまま収録されておる(笑) い着替えるタイミングを間違ったのか、カメラの前でおっぱいポロリ!なんて場面もそのまま収録されておる(笑)
随分と昔パリに行く時、飛行機の中で女性スタイリストさんが隣の席になったことがあるんじゃが、彼女は「この仕事の何が大変かって、モデルがアホで生意気で全然こっちの言うことを聞かないことなの。 こっちはデザイナーから指示されてるのによ!」なんて言っていたのを思い出してしまい、「大勢の美女たちを一言で統制してしまうアルマーニって、やっぱスゴイのお~」と(笑)
本作は密着取材ということなんで、アルマーニのデザイン制作現場なんかがあるんじゃないか?と期待したが、やはりそれはまったく無し(笑) その代わりに幅広い交友関係が惜しげもなく披露されており、エリック・クラプトンやリッキー・マーチンまで登場するぞ。 アルマーニは彼らの演奏を心から楽しんでおるようではあるが、視線だけは異常にスルドイ。 着こなし方をチェックしていたんじゃろうな。 「ファッションの基本は着心地」を強調しとるアルマーニじゃが、一流ミュージシャンのギタープレイやステージアクションに、自らのファッションをいかに融合させていくべきか、 そんな事を思案しとる目じゃな!
10年ぐらい前じゃったかな。 アルマーニが「西洋人と体型の違う東洋人に私のファッションは似合わない」と発言したとかで物議をかもしたことがあったが、 どうか我々日本人もビシッとキメられる一着を発表してもらいたいもんじゃ。(って買えるかどうか分らんけど?!)
★ファッション・デザイナー編② ★ 「ファッションを創る男~カール・ラガーフェルド(2007年)
ファッションとは儚く危険で理不尽だ
 アルマーニに続くファッション・デザイナー・ドキュメントの紹介は、シャネル、クロエ、フェンディといった女性セレブ・ブランドのデザイナーであるカール・ラガーフェルドじゃ。 こちらは2年間約200時間にわたって撮り集められた映像から緻密な編集がなされており、ドキュメントというよりはアンソロジー的映像集と言えるじゃろう。 アルマーニに続くファッション・デザイナー・ドキュメントの紹介は、シャネル、クロエ、フェンディといった女性セレブ・ブランドのデザイナーであるカール・ラガーフェルドじゃ。 こちらは2年間約200時間にわたって撮り集められた映像から緻密な編集がなされており、ドキュメントというよりはアンソロジー的映像集と言えるじゃろう。
どこかビジネスマンとしての鋭利なセンスが漂うアルマーニに対して、ラガーフェルドは風貌もライフスタイルもアーティスト然としておるようで、それ故か、期間限定でぴったりと張り付いて行われる随行取材よりも、時間をかけて集めた取材マテリアルからのセレクト&編集の方がラガーフェルドの実体を浮彫にするには相応しいかもしれんな。
本が山の様に積まれて、色んなブツが乱雑に置かれた仕事部屋。 自宅として使用されておるホテルの部屋や食事の光景。 また実際にデザイン画を作成する場面まで披露されており、これまで謎多きカリスマと呼ばれたラガーフェルドの素の姿をかなりの時間にわたって拝むことが出来る。 まあ紙とペンでデザインしておる光景なんかはあくまでも“撮影用”じゃろうし、ラガーフェルドのモンスターな才能の出処を盗み見ることには繋がらないが(笑)、修正液まで絵筆として使いながらその場で完成させてみせたラフデザインも十分に斬新なインパクトのある出来じゃ。 本作最大のサービス映像じゃろうな!
これはアルマーニにも共通しておるが、作品を作り上げる際に常に一流のモデルが着用したシーンをラガーフェルドは想定しており、撮影の際のモデルのメイクアップや立ち振る舞いにも厳しいチェックを入れるのじゃ。 その為にラガーフェルドは専門のカメラ撮影技術を習得して、自らカメラマンとしてモデルを撮影する。 自分が描いた作品の最高 のイメージを最後まで責任をもって実現させようとしておるのじゃ。 「着心地と動き」といった機能性を重視するアルマーニに対して、ラガーフェルドは少なくとも本作内の描写においては、作品をまず美術品として世に送り出すことを優先しておるような姿勢じゃ。 のイメージを最後まで責任をもって実現させようとしておるのじゃ。 「着心地と動き」といった機能性を重視するアルマーニに対して、ラガーフェルドは少なくとも本作内の描写においては、作品をまず美術品として世に送り出すことを優先しておるような姿勢じゃ。
しかし本作の中でラガーフェルドは自分が先天的な同性愛者であることをカミングアウトしており、その彼がアーティスティックな女性美を追求するという“矛盾”にわしなんかは途中から付いて行けなくなった(笑) ラガーフェルド・デザインで着飾ったニコール・キッドマンらの超セレブ女性の訪問シーンが幾度となく登場するだけに、もし同性愛を生理的に理解できない者が観たら、ラガーフェルドと自分との距離が鑑賞時間の経過とともにどんどん離れていってしまうのを感じるじゃろう。 そんな鑑賞者を突き放していく魅力も本作のセールス・ポイントなのかもしれんがな! ラガーフェルドにとって女性とは、「造形美追求」の対象なのかもしれんっつったら、女性ファンから突き上げを喰らうじゃろうけど?!
ラガーフェルドが女性ファッション専門のデザイナーであるのか否かはわしは知らんけど、男性に関しては熱心に写真撮影のモデルに起用するシーンもなかなか見応えがある。 女性ファッションの放つオーラとは別種の、時代が設定した美意識を突き抜けようとする様な新しい肉体美が匂い立ってくるような写真をラガーフェルドは追求しておるように見える。 この独特の探求心とセンスとが、いかに女性ファッションの創造と融合していくのか? その辺なんかが興味ある方は要チェックの作品じゃ。
★ ヘアデザイナー編 ★ 「ヴィダル・サスーン」(2010年)
従うか、変えるか、ふたつにひとつだ!
 「ハサミひとつで革命を起こした男」、それがヴィダル・サスーン。 女性のヘアカット史において、1950年代から従来の逆毛に盛り上げたオカマ・ヘアーをスプレーで固めた旧式のスタイルを一掃し、「ボブ」「ファイブ・ポイント・カット」といった斬新なカットから「ウォッシュ・アンド・ゴー」(洗ったらそのままでヨシ!)というヘアキープ・スタイルまで提案して世界中に一大旋風を巻き起こした、まさにヘアデザイナーの革命児と呼べる人物じゃ。 「ハサミひとつで革命を起こした男」、それがヴィダル・サスーン。 女性のヘアカット史において、1950年代から従来の逆毛に盛り上げたオカマ・ヘアーをスプレーで固めた旧式のスタイルを一掃し、「ボブ」「ファイブ・ポイント・カット」といった斬新なカットから「ウォッシュ・アンド・ゴー」(洗ったらそのままでヨシ!)というヘアキープ・スタイルまで提案して世界中に一大旋風を巻き起こした、まさにヘアデザイナーの革命児と呼べる人物じゃ。
まあわしは野郎なんで女性のヘアスタイルについてはよお語ることが出来んけど、ヴィダル・サスーンによってもたらされたヘア・スタイルは、ロックンローラーも巻き込んで爆発した60年中期の大ヤング・カルチャー・ブーム「スウィンギング・ロンドン」を彩った女性モデルたちに大人気じゃったんで、かねてより激しく注目しておった。 なんせ当時の名だたる女性モデルたちはほぼ例外なくサスーン・カットを求めておったのじゃ。 最たる例は、ミニ・スカートの発案で時代の寵児となったファッション・デザイナーのマリー・クワント、更にマリーの専属モデルといっても差し支えないツィッギーもヴィダル・サスーンのヘアカットによってそのセンスが開花したのじゃ。
本作を観賞してもっとも驚いたのが、サスーン本人が極めて穏やかな人格者っぽい事実じゃった。 どんな分野であれ、革命児と呼ばれる者の実像は得てして過剰な自信家であり、極めてアグレッシブでエキセントリックな性格じゃ。 発言も当然のごとく挑戦的であり、旧体質然とした業界に対するアンチテーゼを語る時の目は、お歳を召されてからの昔話の時でさえも闘士そのものじゃ。
じゃがサスーンは、業界の旧体質の良き部分、有難き思い出に対しては常に誠実に語っておる。 最初に師事したお師匠に対して、美容室における従業員の「礼儀正しさ」「清潔感」の重要性を学んだと明言。 また次の師事先で門前払いを喰らった際の「まず正しい英語の発音を学んでいらっしゃい」というアドバイスを素直に実行し、「接客業の基本を教えて頂いた」と感謝の念を作品中で繰り返し述べておる。 サスーンは元々ユダヤ人であり、ブロークンな英語しか喋れなかったのじゃ。 「新しいスタイル」を求めたり会得することは、何でもかんでも旧スタイルに「No!」をつきつけることでは決してないことをサスーンの言葉からあらためて教えてもらったわい!
そうした謙虚な姿勢があったからこそ、古いスタイルに固執する同業者、愛好者からの非難、嫌がらせも最小限に留められたに違いない。 このドキュメンタリー映画の紹介に当たり、ネットでサスーンの情報記事 を色々とチェックしてみたが、新しいお客さんに対して「私のカットを信用しなさい」とか「あなたのこれまでスタイルはおかしい」といった傲慢な言動があったとされておるが、本作のサスーン像の描写を観た限りでは、それは真実ではなさそうじゃ。 を色々とチェックしてみたが、新しいお客さんに対して「私のカットを信用しなさい」とか「あなたのこれまでスタイルはおかしい」といった傲慢な言動があったとされておるが、本作のサスーン像の描写を観た限りでは、それは真実ではなさそうじゃ。
ヘアカットに関してのサスーンの信念は極めてシンプルなようじゃ。 ヘアカットする者の顔の骨格とヘアの生え方(流れ)を最重要視してからスタイルを決めるとのこと。 細かい部分はよく分からんけど、ナチュラル・ファーストってことじゃな! “とってつけたような”過剰なもりもりヘアーは、女性が持って生まれたその人独自の美しさを損ねているのではないか?という若き日の消し難き疑問がサスーン・カットの根底に流れておるそうじゃ。 女性それぞれが持って生まれた美しさを見極めるにはどんな修行が必要なのかってことを知りたくなったが、その辺はあんまり語られずじまい(笑)
あえてヒントがあるとすれば、それは母親の思い出バナシかのお。 サスーンの母親は夫に捨てられ、貧しさからサスーンを孤児院に長らく預けたものの、サスーンの特性を見抜いて早くから「手に職を付ければ男はどこででも生きていける」「ハサミを持って美容師を目指しなさい」と月に一回だけ許される孤児院の面会の機会にサスーンに言い聞かせたという。
それは幼いサスーンにとって、女性の強さ、優しさの本質を母親の言葉から感じ取ることの出来る機会であり、女性の本当の美しさを母親の気丈な姿勢から学んでいたのかもしれない。 愛する母親との数少ない面会が、サスーンの女性に対する鑑識眼を磨いたってことか。
★デパート従業員編 ★ 「ニューヨーク・バーグドルフ~魔法のデパート」(2012年)
私が死んだらバーグドルフに遺灰を撒いて!
 ニューヨークの一等地・五番街にある創業100年を越える老舗ファッション・デパートが「バーグドルフ・グッドマン」。 グッチ、ドルチェ&ガッパーナ、クリスチャン・ディオール、イヴサンローランなど数多くの超一流ブランドが確保されていることは言うまでもなく、一方では個性的な新進なデザイナーズ・ショップもあり、また魅惑的なウィンドーディスプレーなども評判が高く、世界中の超セレブたちの憧れのデパートじゃ。 ニューヨークの一等地・五番街にある創業100年を越える老舗ファッション・デパートが「バーグドルフ・グッドマン」。 グッチ、ドルチェ&ガッパーナ、クリスチャン・ディオール、イヴサンローランなど数多くの超一流ブランドが確保されていることは言うまでもなく、一方では個性的な新進なデザイナーズ・ショップもあり、また魅惑的なウィンドーディスプレーなども評判が高く、世界中の超セレブたちの憧れのデパートじゃ。
本作は同デパートの裏側に密着し、創業者をはじめとして、CEO、ファッション・ディレクター、販売担当者、社員教育担当者、ディスプレイ責任者等、デパート経営に関わる様々な人々、また同デパート内に出店を許された新旧のデザイナーたちのインがタビューで埋め尽くされておる。
わしは実際にこのデパートに行ったことはなく(行っても門前払いかのお!)、超高級ブランドには興味がない(というか端から相手にされていない?!)ので何がどうスゴイのかサッパリ分からん。 デパート関係者のインタビューは、皆さん自分のお仕事に対してむせかえるようなプライドを放っておって、最初は相当不快じゃった(笑)
出店を許された新進のデザイナーさんたちも、「バーグドルフに認められるとは、なんて幸せ&オレってスゲー!」ばっかりで「あぁ、そうですか」以上の感想は無い?! 大体有名な女性ファッション・ディレクターさんのファッションそのものが、ちっともセンスがいいとは思わない。(生地は最高級なんじゃろうが)
アルマーニやラガーフェルドといった超一流デザイナーのインタビューの登場するが、それも「大きなビジネス展開に繋がった有難いデパート」って程度の発言であり、ちょっとインタビュアーの質問が、ドキュメンタリー映画製作のレベルからいったらお粗末過ぎ。 まあ出演者の自画自賛のオンパレードなんで、実際の超セレブな顧客は大喜びじゃろうが、一般の映画鑑賞者の視線はまったく考慮されておらんわい。
とは言っても、さすがは超一流デパート。 わし自身のレベルを度外視して見直すと(笑)、超セレブたちにいかにして最上級の満足を与えるかって事に命をかけておる従業員たちの姿勢は迫力があって見ものじゃ。  超セレブさんってのは、欲しいものは大概手に入れることが出来るわけだから、物欲への執着度はパンピーの想像の域を超越しとるわけじゃ。 そんな彼らを満足させるもの、それは究極的には「世界に二つとないもの」「自分だけが持っておるもの」なんじゃろう。 それを探し出し、もしくは創り上げさせるのがデパート側の使命であり、生半可なやる気、緊張感、責任感では勤まらんじゃろう。 超セレブさんってのは、欲しいものは大概手に入れることが出来るわけだから、物欲への執着度はパンピーの想像の域を超越しとるわけじゃ。 そんな彼らを満足させるもの、それは究極的には「世界に二つとないもの」「自分だけが持っておるもの」なんじゃろう。 それを探し出し、もしくは創り上げさせるのがデパート側の使命であり、生半可なやる気、緊張感、責任感では勤まらんじゃろう。
当然彼らには狂気が芽生え、過剰が漲り、「金ならナンボでも出す」といったある種傲慢なお客と対等に張り合えるだけの武器が必要じゃ。 その武器とは自分自身なわけで、その発言もぶっ飛んでいて然り! 「我々はお客様視線をモットーにしておりまして~」とか「最近のお客様のニーズの傾向はなんたらかんたら」なんてコメントは似合わない!
「バーグドルフ・グッドマン」の従業員にとって、お客様は「愛すべき敵」であり、職場は「戦場」なのじゃ。 物販業を「戦争」と比喩するのはいささか見当外れかもしれんけど、案外このデパートの隠れたモットーは「超セレブたちをぐうの音も出ないほど叩きのして金を叩きつけさせろ!」かもしれんぞ(笑) そんな風に想像しておけば、見れば見るほど痛快なドキュメント映画になるぞ!
最後に一言。 ジョン・レノンとオノ・ヨーコも顧客として登場するが、「ジョンとヨーコが一度に80着も毛皮のコートを買ってくれた」ってだけの紹介は、ロックファンとしては止めてほしかった!
|

ご存知ファッション・デザイナーの大御所ジョルジュ・アルマーニの、世界を飛び回る1年間の行動を編集したドキュメンタリーじゃ。 2000年夏のミラノ・コレクションに出品する服のデザインから、モデルのウォーキング、時間配分まで細かく指示を出すアルマーニ。 同年秋に開店するパリの新店舗づくりにおいて、足繫く通いながら建築資材まで入念にチェックするアルマーニ。 ニューヨーク・グッゲンハイム美術館において、自身の個展という新しい企画に対して激しく思案するアルマーニ。 さらにスタッフとの離れ小島での余暇の様子などを含めて、多忙を極めるアルマーニの姿が活写されておる。
い着替えるタイミングを間違ったのか、カメラの前でおっぱいポロリ!なんて場面もそのまま収録されておる(笑)
アルマーニに続くファッション・デザイナー・ドキュメントの紹介は、シャネル、クロエ、フェンディといった女性セレブ・ブランドのデザイナーであるカール・ラガーフェルドじゃ。 こちらは2年間約200時間にわたって撮り集められた映像から緻密な編集がなされており、ドキュメントというよりはアンソロジー的映像集と言えるじゃろう。
のイメージを最後まで責任をもって実現させようとしておるのじゃ。 「着心地と動き」といった機能性を重視するアルマーニに対して、ラガーフェルドは少なくとも本作内の描写においては、作品をまず美術品として世に送り出すことを優先しておるような姿勢じゃ。
「ハサミひとつで革命を起こした男」、それがヴィダル・サスーン。 女性のヘアカット史において、1950年代から従来の逆毛に盛り上げたオカマ・ヘアーをスプレーで固めた旧式のスタイルを一掃し、「ボブ」「ファイブ・ポイント・カット」といった斬新なカットから「ウォッシュ・アンド・ゴー」(洗ったらそのままでヨシ!)というヘアキープ・スタイルまで提案して世界中に一大旋風を巻き起こした、まさにヘアデザイナーの革命児と呼べる人物じゃ。
を色々とチェックしてみたが、新しいお客さんに対して「私のカットを信用しなさい」とか「あなたのこれまでスタイルはおかしい」といった傲慢な言動があったとされておるが、本作のサスーン像の描写を観た限りでは、それは真実ではなさそうじゃ。
ニューヨークの一等地・五番街にある創業100年を越える老舗ファッション・デパートが「バーグドルフ・グッドマン」。 グッチ、ドルチェ&ガッパーナ、クリスチャン・ディオール、イヴサンローランなど数多くの超一流ブランドが確保されていることは言うまでもなく、一方では個性的な新進なデザイナーズ・ショップもあり、また魅惑的なウィンドーディスプレーなども評判が高く、世界中の超セレブたちの憧れのデパートじゃ。
超セレブさんってのは、欲しいものは大概手に入れることが出来るわけだから、物欲への執着度はパンピーの想像の域を超越しとるわけじゃ。 そんな彼らを満足させるもの、それは究極的には「世界に二つとないもの」「自分だけが持っておるもの」なんじゃろう。 それを探し出し、もしくは創り上げさせるのがデパート側の使命であり、生半可なやる気、緊張感、責任感では勤まらんじゃろう。
“パンク”っつっても、ロッカーじゃない! チャールズ・ブコウスキーとは、20世紀最後の“無頼派作家”と呼ばれたアメリカ人の物書きさんじゃ。 かつてミック・ジャガーが「俺はキース(リチャーズ)ほどパンクなヤツは知らない」って言っておったが、この七鉄は「キースよりブコウスキーの方がパンクじゃ」と言っておこう(笑)
リソンの「これで終わりだ」なんて「ふざけるなっ!」、ルー・リードの「ワイルドサイドを歩け」なんて「“おととい来やがれ”!」ってトコじゃなあ・・・。
星印の付いたベレー帽をかぶったゲバラの顔写真はあまりにもカッコよくて、今や日本でもTシャツやタバコのパッケージにもあしらわれており、ゲバラの名前やキャリアを知らない人でも一度は目にしたことがあるじゃろう! 「この人、有名ロックミュージシャンなの?」なんてカノジョさんから聞かれたりしたカレシさんもいっぱいおるじゃろうな! 男も女も惚れてしまうような、インテリジェンスと反逆のオーラが漂う超男前な顔写真じゃって、いきなり話が横道に逸れてしまったな!(笑)
美しいが、救い難いほど青臭い。 そして最期はボリビア軍に捕らえられて死刑に処されてしもうた。 英雄と呼ばれたゲバラの最期はあまりにも無残じゃった。
最後にスポーツものをひとつ加えておこう。 本作はアメリカ・メジャー・リーグ・ベースボール機構が製作したオフィシャル映像集シリーズのひとつであり、メジャーリーグ史に輝く剛速球投手、剛腕投手が数多く紹介されておる。 通算5714奪三振というとてつもない大記録を作ったノーラン・ライアン、4672奪三振(歴代2位)のロジャー・クレメンスというテキサスが生んだ二大剛腕投手のドキュメンタリー的な紹介に時間がかなり割かれておるものの、他の有名投手の貴重な映像も次々と登場するので、スリリングな事この上なし!
違う」ベースボールってヤツを観せられておるようじゃ。 今年のWBCでは本家アメリカが初めて本気になって優勝したが、そのアメリカ・チームの投手すら小粒に感じてしまうほど、歴代の剛腕投手の雄姿はケタハズレにスゴイ。