
NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN VOL.191

NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN VOL.191
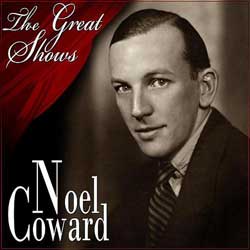 このところ、ポール・マッカートニー&ストーンズの来日ネタや、過去の名盤を紹介する事ばかりやっており、あんまりファッション関連の事を書いておらん。 久しぶりに「連載:ダンディと呼ばれし男」を再開させて頂くことにするぞ。 このところ、ポール・マッカートニー&ストーンズの来日ネタや、過去の名盤を紹介する事ばかりやっており、あんまりファッション関連の事を書いておらん。 久しぶりに「連載:ダンディと呼ばれし男」を再開させて頂くことにするぞ。実はこの連載を読んで頂いておる知人から、先日キツイご指摘があった。 「19世紀とか20世紀初頭のダテ男ばっかりはいいとしても、社交界のダンディなんて、パトロンあってのダンディだろう? 全然ダンディじゃなくね?」 ・・・え、ええ、まあ、現代の視点から見ればそう言えなくもないし、「ダンディだからこそパトロンが付くんじゃ!」って反論しても「卵が先か鶏が先か」のごとく!?結論は出そうもない。 じゃあこの際、ムチャクチャ仕事をした伝説の残るダンディを紹介してみようかのお。 The-Kingから極上フラップシューズが発表され、足元もバッチリとキマって仕事にも俄然気合の入ったところなんで、必殺仕事人!にご登場頂くには悪くないタイミングでもあるしな! これから紹介するダンディ、あのブラックとバーガンディのフラップシューズも似合いそうじゃ! その名はノエル・カワード。 1920〜40年代にイギリスで超人気を誇った、舞台劇作家、監督、俳優、そして作曲家じゃ。 お年を召してからも、あのエリザベス・テーラーらの銀幕の美女たちが、共演を熱望していたほどのダンディであり、 ロック界でもポール・マッカートニー、デヴィッド・ボウイ、ブライアン・フェリーらがノエル・カワードに傾倒しており、「ノエル賛歌」も存在するほどの存在じゃ。 自らの巨大な才能を活かして数多くの舞台劇を生み出し、また自ら演じることで巨額の富を手に入れ、それを活かしてセンスのいいセレブ生活を生涯満喫していた「ザ・トップ・オブ・芸能人」でもある。 「私は人生をファーストクラスで旅することに決めているんだ!」 と公言してはばからなかったノエル・カワードとは、一体どんなダンディだったのか? ダンディと呼ばれし男:第9回〜ノエル・カワード ファースト・クラスの人生を楽しんだ、「うわべ人」にして「モーレツ仕事人」 黄金の「ブライト・ヤング・シングス時代」のシンボル  第一次世界大戦が終わった1920年代のイギリスにおいて、暗い世相を吹っ飛ばすようなヤング・カルチャーがブームになった。 と言ったら大げさになるが、実は「お酒やパーティーやファッションを自由に楽しむ若者が急増した」というだけのハナシ。 じゃがそれはイギリス史上初めての現象だったんじゃよ。 同時期、アメリカでは「ジャズ・エイジ」と呼ばれてジャズに熱狂しながら遊戯的な人生を謳歌する若者が増え、娯楽そのものも飛躍的に発展して「狂騒の1920年代」を迎えることになるが、イギリスでも似たようなブームが起きておったのじゃ。 第一次世界大戦が終わった1920年代のイギリスにおいて、暗い世相を吹っ飛ばすようなヤング・カルチャーがブームになった。 と言ったら大げさになるが、実は「お酒やパーティーやファッションを自由に楽しむ若者が急増した」というだけのハナシ。 じゃがそれはイギリス史上初めての現象だったんじゃよ。 同時期、アメリカでは「ジャズ・エイジ」と呼ばれてジャズに熱狂しながら遊戯的な人生を謳歌する若者が増え、娯楽そのものも飛躍的に発展して「狂騒の1920年代」を迎えることになるが、イギリスでも似たようなブームが起きておったのじゃ。当然そうした風潮を美化して先導する一派がおり、彼らは「ブライト・ヤング・シングス(輝ける若者たち)」と呼ばれることとなり、その先頭に立っていたのがこのノエル・カワードだったのじゃ。 まだまだ映画の本数も少ない時代だっただけに、庶民の優雅な娯楽の代表は演劇鑑賞じゃ。 ノエル・カワードは演劇作家として次々と大ヒット作品を発表し、自ら監督も務め、また俳優としても舞台に上がって喝采を浴び、当時のイギリス芸能界きってのマルチ・アーティスト、トップスターに登り詰めたのである。 「私はケタハズレの才能に恵まれた男だ。 才能のないフリをすることなんてできない!」とまで豪語しておったが、その言葉通りの大活躍をしておったんじゃ。 ちなみにこの「ブライト・ヤング・シングス」時代の別のスターにハロルド・アクトンという俳優がおった。 このアクトンこそ、オックスフォード・バッグ、つまりThe-King製の幅広のパンツの原型スタイルのパンツを最初に流行させた者じゃ。 The-Kingアイテムの源流のひとつは「ブライト・ヤング・シングス」時代でもあるのじゃ〜♪ 時代を風靡したドレッシング・ガウン!  「ブライト・ヤング・シングス」のシンボルとして君臨したノエル・カワード。 もっとも気になるのはファッションじゃ。 彼のトレードマークになったのは、まず頭皮にピッタリとなでつけた髪の毛。 右写真は、1930年撮影のオックスフォード大学のボート部部員たちの雄姿。 ほとんどがオックスフォード・バッグを履いておるが、注目してほしいのは、彼らの髪型。 みんなナチュラルな分け目に合わせて髪の毛を綺麗になでつけておる。 「ノエル・カワード流ヘア・スタイル」の影響力を物語る証明写真じゃよ! スーツにおいては仕立ては上物にしてスタイルはオーソドックス。 当時アメリカで流行していた、フィット感の強い「ジャズ・スーツ」に近いと言えるかもしれない。 これはノエル・カワードが舞台俳優でもあるが故に、動作をよりシャープに、よりダイレクトに聴衆に伝えるアイディアだったとも言えるじゃろう。 そしてアンダーのシャツは常にシルク。 シルクのシャツは当時の上流社会の象徴でもあった。  更にもうひとつのトレードマークになったのはシルクのドレッシング・ガウン! 1924年に発表された、劇作家としてのノエル・カワードの最初のヒット作「渦巻き」の舞台において自ら着用することで大いに注目を浴びたアイテムであり、以降ノエル・カワードは様々な柄のガウン姿でマスコミの前に登場し、時にはソファーに寝そべりながらインタビューを受けたりしておった。 更にもうひとつのトレードマークになったのはシルクのドレッシング・ガウン! 1924年に発表された、劇作家としてのノエル・カワードの最初のヒット作「渦巻き」の舞台において自ら着用することで大いに注目を浴びたアイテムであり、以降ノエル・カワードは様々な柄のガウン姿でマスコミの前に登場し、時にはソファーに寝そべりながらインタビューを受けたりしておった。寝室着の域を出ていなかったガウンをアピールしたノエル・カワードのファッション哲学とは、「極めてプライベートな空間でも  、お洒落に拘る」ということじゃ。 後年、デヴィッド・ボウイが「世界を売った男」というアルバムのカヴァーで、この「ノエル・カワード・スタイル」を意識したポーズをとっておる。(右写真参照) 、お洒落に拘る」ということじゃ。 後年、デヴィッド・ボウイが「世界を売った男」というアルバムのカヴァーで、この「ノエル・カワード・スタイル」を意識したポーズをとっておる。(右写真参照)このメンズ・ドレッシングガウンは、男前を自負するイギリス野郎どものハートを射抜き、優雅に朝食をとったり、そのまえにかる〜く仕事を片付けたりする時の粋なファッションとして大人気となった。 また首にスカーフを巻きつけたスタイルやタートルネックのセーターは、ノエル・カワードが庶民に流行らせたもんなんだそうじゃ。 「見せかけ」「うわべ」こそ、「ダンディズム」の真髄!?  ダンディズムに生きる男には、誰しも「絶対に譲れないスピリット」がある。 拘りの強さこそ、その者のイメージを決定し、そのイメージを全うする事がその者固有のダンディズムになっておる。 ただしダンディを支えるそのスピリットってのは、歴代のダンディにおいては禁欲的で堅苦しくてマネ出来ないというか、したくないというか、ダンディってもんがいかに庶民の精神性とは別次元に存在しているかを物語っておる。 さて、ノエル・カワードのダンディとしてのスピリットは何だったのか? ダンディズムに生きる男には、誰しも「絶対に譲れないスピリット」がある。 拘りの強さこそ、その者のイメージを決定し、そのイメージを全うする事がその者固有のダンディズムになっておる。 ただしダンディを支えるそのスピリットってのは、歴代のダンディにおいては禁欲的で堅苦しくてマネ出来ないというか、したくないというか、ダンディってもんがいかに庶民の精神性とは別次元に存在しているかを物語っておる。 さて、ノエル・カワードのダンディとしてのスピリットは何だったのか?意外や意外、ノエル・カワードのダンディズムとは、 「『見せかけ』『うわべ』こそ、人生のモットー」 だったのじゃ! なんじゃ、そりゃ!?じゃが、勘違いをするなかれ。 物事の見てくれにしか興味がないという「軽薄短小万歳!」って事ではないぞ。 それは「美」のあり方への拘り方とでもいうべきか。 冒頭でノエル・カワードをモーレツ仕事人って書いたが、それはヒットする舞台劇を休み間もなく発表し続け、自ら舞台に立ち続けたことであるが、その理由は 「美しいものは長くは続かない。 人々の気持ちも移ろいやすいもの。 ならば、新しい美を作り続けるべきだ」 という信念に基づいておるのじゃ。 実際に自分の作品がロングラン興行に成ることを嫌ったために、新しい作品を発表し続けていたのじゃよ。 「花瓶の花はせいぜい二日か三日しかもたない」という儚さへの執着、愛着じゃ。 だからこそ「見せかけ」「うわべ」を大切する。 そして深追いはしないってことじゃ。 「大ヒット一曲で、生涯安心の印税生活」なんてのを夢見ておるどっかの小国の“芸No人”に爪の垢でも煎じて飲ませてやりたい! 更に発表される作品は、愛だの恋だの、同性愛だの、不倫だの略奪愛だの、パーティだのドライブだの、酒だのドラッグだの、ほんのひと時の享楽に溺れる人間の可笑しさ、儚さ、愚かさをかる〜いタッチでオモシロオカシク、オシャレに表現したものがほとんど(らしい、というか、わしは観ておらんのでな)。 もちろんその奥また奥には表現者としての哲学があるのじゃが、あくまでも表面的には華やかにシャンパンの香りの様に、かる〜くいこう〜♪がノエル・カワード流舞台劇。 だから、それまで舞台と言えば、大上段に振りかぶったシェイクスピア劇一辺倒だったイギリス人に喝采をもって迎えられたんじゃろうな。 庶民が夢見る上流社会を再現する様々な小道具が舞台に散りばめられ、そこで繰  り広げられる世界は、一見「悩みなんて無し」の優雅でうつろいやすい恋愛ゲームの様な人間模様。 「青春とは何ぞや?」「苦悩の果てにあるものは?」「幸せとはどこにあるのか?」っつったオモ〜イテーマは一切お呼びじゃあなかった! り広げられる世界は、一見「悩みなんて無し」の優雅でうつろいやすい恋愛ゲームの様な人間模様。 「青春とは何ぞや?」「苦悩の果てにあるものは?」「幸せとはどこにあるのか?」っつったオモ〜イテーマは一切お呼びじゃあなかった!一説によると、ノエル・カワードは晩年においてビートルズが快進撃を繰り広げている時、イギリス芸能界の長老の中では珍しく「この子たちは凄い!」とビートルズを素直に認めたとも言われておる。 自分達で曲を書き、歌い、演奏をする。 またそれがことごとく大ヒットするビートルズのマルチな活躍に、若き日の自分自身を重ねあわせていたそうな。 それを伝え聞いたポール・マッカートニーは感激して、わざわざノエル・カワードに会いにいったらしい。 もっともノエル・カワードは、ビートルズが4人揃ってやって来なかったことに少々オカンムリだったとか! プライドに拘る狂犬は見苦しい  わしがノエル・カワードの名を最初に知ったのは、実はロックのレコードのタイトルじゃった。 それはジョー・コッカーという60〜70年代に活躍した超パワフルなブルース・ロック・シンガーのライブ盤「マッドドッグス&イングリッシュメン」じゃ。 「マッド・ドッグ(狂犬)ってジョー・コッカーのイメージだな」って漠然と思っていたが、実はノエル・カワードが書いた曲のタイトルからの引用だったんじゃ。 「クソ暑い日に外に出て暴れているのは、狂った犬かイギリス人ぐらいさ!」って歌じゃ。 何でも熱帯地方のたくさんのイギリス植民地で、額に“激汗”して働くイギリス人への皮肉らしい。 わしがノエル・カワードの名を最初に知ったのは、実はロックのレコードのタイトルじゃった。 それはジョー・コッカーという60〜70年代に活躍した超パワフルなブルース・ロック・シンガーのライブ盤「マッドドッグス&イングリッシュメン」じゃ。 「マッド・ドッグ(狂犬)ってジョー・コッカーのイメージだな」って漠然と思っていたが、実はノエル・カワードが書いた曲のタイトルからの引用だったんじゃ。 「クソ暑い日に外に出て暴れているのは、狂った犬かイギリス人ぐらいさ!」って歌じゃ。 何でも熱帯地方のたくさんのイギリス植民地で、額に“激汗”して働くイギリス人への皮肉らしい。「度を越した愛国心、プライドとは何と愚かなものよ」 「目の前にあっても見えていない小さな美の命を尊ぶ方がはるかに人間らしい」 ってメッセージじゃな。 世界情勢は大英帝国からアメリカ合衆国の手に移り、イギリスが過去の栄光に固執している時代にこの皮肉! 同時にノエル・カワードは「戦争は憎しみの舞台であり、私には向いていない」と発言して、一時は非国民扱いを受けたらしい。 それでも旧友だったウィンストン・チャーチル海軍大臣は、「あんなヤツ、戦争に行っても何の役にもたたない。 一人ぐらい、愛だ恋だって歌ってるヤツがいたっていい」とノエル・カワードをかばったそうじゃ。  ボー・ブランメルやリットン卿などが社交界を闊歩していた19世紀に比べると、ノエル・カワードが生きた20世紀のダンディはかなり様相が変わってきておるな。 第7回で紹介した、ジェームズ・ボンドの生みの親イアン・フレミングもそうじゃが、やはり「仕事が出来てナンボ!」、そして仕事の成果も、絶えることなく継続させねばならんってのがダンディのスタート地点になっておる。 わしの様に、7年以上もの歳月の中でたかだか「連載200回程度」にフウフウ言っとる様なヤツはお呼びじゃないのお(涙) The-Kingのボスの様に、毎回ファンを驚喜させるようなアイテムを連発できる男がダンディの資格があるってことじゃ。 また、そんなThe-Kingを支え続けていらっしゃる諸君の方が、老い先短い?わしより「真のロックンロール・ダンディ」になる素養も可能性もあるなあ。 やはり夢は諸君に託すしかない。 お買い物の方、よろしく頼んだぞ! (って、いつもわしがそぉ〜と先に買っとるけどな!) それでも最後にかましておきたい。 ノエル・カワードの残した、わしの大好きな言葉を。 「仕事は最大の“お楽しみ”だ。 ただの“お楽しみ”よりはるかに楽しい」 う〜ん。 それでいて「見せかけ」と「うわべ」に拘る。 まさに新しいダンディズム、アッパレじゃ! |
|
七鉄の酔眼雑記 〜部屋の中でもナリをキメろ & メシはガツガツ食え!? 今回取り上げたノエル・カワードが、誰にも会わないプライベートな空間でもファッションにこだわっていた事を紹介したが、諸君、これ出来るか? わしはどうもねえ〜(苦笑) 人目を気にしない所では、どうしてもファッションはいい加減になるというか、はっきり言って、上下の組み合わせの色を気にするぐらいで、ひたすらリラックスできる物を身に着けてしまう。 いや、リラックスというより、寝転んでも、寝てしまってもいい服装になってしまう! またまた1977年のわしのイギリス滞在期のエピソードをご紹介するが、この時現地の一般家庭にホームステイしたんじゃが、その家のご主人が部屋の中でも革靴を履いたまんまってのは驚いた! そのご主人はマイケル・ダグラスばりの美男子でオシャレ。 就寝直前にパジャマに着替えるまで、バッチリとキメた外出着のまんまだったのも衝撃的じゃったな。 そんな恰好じゃ、自分の家の中でリラックスできないじゃないか!って当時は思ったが、単なる生活習慣の違いというよりも、「リラックスする(のんびりする)」と「休む」との違いを、この時にスルドク気が付くべきじゃった! 20代の頃よりいまだに続いておる、部屋に戻ったらソッコーでジャージに着替えてゴロ〜ン♪してビール飲んで(笑)って悪習慣とは無縁でいられたかも!? 「リラックス」はまだまだ機能稼働中、「休み」は機能停止中なのじゃ。 話のついでにイギリスの一般家庭の習慣をもうひとつ。 わしは都合3件の家にホームステイしたが、どこの家庭も夕食中は基本的にみんな無口でひたすら食べ続ける。 家族全員で早食い競争をやってるみたいであり、これにも参ったもんじゃ。 食事中、食器の音がテーブルの上で交差しとるだけでスンゲー不気味じゃった。 料理の味なんかせんわい! 一応、居間のテレビはつけっぱなしなんだけど、そんなもんは眼中になく、みんな食べることに集中しておる、というよりは食べ物を目の前から消すことが目的みたいなんじゃよ。 イギリスの食事は不味いから、とにかく温かい内に食べろ!ってワケなんじゃろうか? そんな“早食い競争”が終わるとティータイムになるが、今度はみんな人が変わったみたいに談笑しながらゆ〜たりとお茶を飲むんじゃな。 メリハリが効いてはおるけど、これも慣れるまで時間がかかったわい。 だってさ、物も言わずに食い続けておったら、親父殿から「ガツガツするな!」、お袋さんから「もっとちゃんと噛んで食べなさい!」って怒られるのが日本じゃもんな。 どの家庭も食事は質素だったし、一度ステイ先の奥様から「競馬で負けちゃったから、お金貨して」って頼まれたこともあったし、ホームステイしたい外国人学生を募る家庭なんで、決して裕福ではなかったんじゃろう。 だから上記の習慣がそのままイギリス人全般に当てはまるとは言えないが、願わくば、ノエル・カワード・クラスの上流は無理としても、中流クラスぐらいの家庭の生活実態もこの目で見てみたかったな〜。 GO TO TOP |