
NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN VOL.176

 “猛暑再び”でファッションへの意識もヘタレ気味な毎日じゃが、自らに喝(かつ)を入れ直すべく、連載「ダンディと呼ばれし男たち」を再開するとしよう。 The-Kingのボスが驚くほどに元気なんで、わしも老骨にムチを振るわないといかんからな! “猛暑再び”でファッションへの意識もヘタレ気味な毎日じゃが、自らに喝(かつ)を入れ直すべく、連載「ダンディと呼ばれし男たち」を再開するとしよう。 The-Kingのボスが驚くほどに元気なんで、わしも老骨にムチを振るわないといかんからな!しっかし、あの目の覚める様な新作シャツのカラーリングは、正直なところ、夏バテって言い訳に逃げ込んでおった自分に冷や水をぶっかけられて覚醒させられた作品じゃ。 カートに放り込むことは、真夏のロックファンとしては当然過ぎるアクションですぞ! 迷うなかれ!! ダンディは、立派な芸術家である必要などない。 何故ならダンディ自身が芸術品であるからだ。 ではでは、この(↑)「不滅のダンディ定義」をブチかました男、オスカー・ワイルドにご登場頂くとしよう〜♪ 左の写真のお方じゃ。 まるで70年代のブリティッシュ・ロック・スターの様じゃな。 スギちゃんじゃないが「ワイルドだろう〜」。 いやいやそうではなくて、いやあ〜ストレンジ(奇妙、奇抜)この上なく、アブナイ男の香りがプンプンするのお。 オスカー・ワイルドは1854年生まれ(1900年没)のアイルランド出身の詩人、作家、劇作家じゃ。 文筆家としての活躍はもとより、そのダンディぶりもまた語り草になるほどの人物じゃった。 ジョージ・ブランメルから始まった「19世紀のヨーロッパ・ダンディ神話」は、その世紀末においてオスカー・ワイルドによって締め括られたといってもええじゃろう。 ワイルドが社交界で活躍した19世紀後半になると、写真技術が登場し、歴史的な人物には多くの実像写真が残されておる。 だから諸君にもより分かりやすく伝わると思えるので、どうか楽しんで読んで頂きたい。 なお今回は、オスカー・ワイルドの作家としての数々の輝かしい功績の記述は最小限に留め、ダンディぶりと生き様に焦点を絞ってお届けする。 ダンディと呼ばれし男たち〜第4回:オスカー・ワイルド 19世紀“ダンディ神話”のラストを飾った、 耽美主義とアフォリズムに生きたダンディ文士 ■ 「耽美主義」とは? 「アフォリズム」とは? ■ え〜まず「耽美主義」ってのはだな、ネット辞書によると 『美に最上の価値を認め、それを唯一の目的とする、芸術や生活上の立場。 19世紀後半、フランス・イギリスを中心に興ったもの』 何やら難しそうじゃが、“美”ってのは色彩的な美しさだけではのうて、“自分の愛する世界への拘りの強さ”って意味も含まれており、これまさにThe-King的じゃな! 一方の「アフォリズム」。 これは読んで字のごとしでわしの事! 「阿呆イズム」じゃあ〜ってバカモノ! 『アフォリズム【aphorism】 物事の真実を簡潔に鋭く表現した語句。 警句。 金言。 箴言(しんげん)』 要するに、心に残る必殺のワンフレーズ、もしくはそういう表現主義のことじゃよ。 パーカー大佐の「君(エルヴィス)の才能を100万ドルにしてみせよう」とか、ジョン・レノンの「エルヴィスが登場して、それまでの事は無かった事になった」ってのも、ロック界のアフォリズムじゃ! では始めるとしよう。 耽美主義とアフォリズムに生きたダンディ文士、オスカー・ワイルドとはどんなダンディ野郎だったのか? ■ もっとも気持ち良く文学を“たしなんだ気にさせてくれた”恩人!? ■  わしがオスカー・ワイルドの名を知ったのは高校生の頃。 文学書が大の苦手で、それこそ「阿呆イズム」しとったわしは、それを克服すべく、まず「著名文学者の名言集」みたいな一種の「アンチョコ(虎の巻的ガイド)」から取り組んだんじゃ。 そこで興味を引いた言葉の発言者の作品なら多少は読み進める事が出来るんじゃないか?という文学オンチの涙ぐましい努力じゃ(笑)。 そんな時に出会ったのがオスカー・ワイルドの数々の言葉。 ウイキペディアから引用するとこうじゃ。 「男は愛する女の最初の男になる事を願い、女は愛する男の最後の女になる事を願う」 「流行とは、見るに堪えられないほど醜い外貌をしているので、六ヶ月ごとに変えなければならない」 「不平や不満は人間にとっても、国家にとっても進歩の第一段階である」 「人間は不可能を信ずる事が出来るが、ありそうもない事を決して信ずることは出来ない」 「外見で人を判断しないのは愚か者である」 「ほとんどの人間は他人である。 思考は誰かの意見、人生は物まね、そして情熱は引用である」 即座に「感動したあ!」とはならんかったが、「ほほぉ。 人間とか人生ってのはそういうものなのか」ってあっさりと納得したのじゃ。 既にロック狂と化していたわしも、どういうわけか心に染みこむ言葉はこんな達観的なスルドサで迫ったものばかり。 その他にも世界中の文学者たちの数々の名言を読んだが、即インプットされた数ではオスカーワイルドがもっとも多かったと思う。 今更ながらに思うが、ワイルドの言葉、アフォリズムは、表面の感触はロックのビートと正反対じゃが、真理は同じだって直観していたのじゃろう。 それに、両親やガッコのセンセは絶対に教えてくれない!トコがロック同様にタマラナイ快感じゃった。 ■ “奇抜”“反抗的”と呼ばれた、古典主義プラス機能主義のファッション ■ 
先述の通り、ワイルドは天才的なアフォリズムのセンスの持ち主じゃ。 更にそいつを語り聞かせる話術にも長けており、イギリスの名門オックスフォード大学留学中からワイルドは周囲の人気者。 成績も優秀で、卒業試験は主席じゃったらしい。 貴族の子息が多数在籍する同校の人気者となれば、当然のごとく社交界への扉も開かれたわけじゃ。 ワイルドのダンディ神話のスタートである! ワイルドが纏ったファッションは、自ら「ワイルドだろう?」と言い放っておった!ではなくてだな、今もなお「奇抜だった」と多くのファッション誌に記載されておる。 その詳細は下記の通りじゃ。 ヘアスタイル・・・かる〜くカールしたやや長髪 ジャケット・・・丈の短いブラック・ヴェルヴェット。 襟と袖にあしらった大きなキルティングがポイント マント(ケープ)・・・カラーが高く、手首まで隠れるウール地のマント ネッククロス・・・シンプルに巻いたモスグリーンのロングタイ パンツ・・・ニー・ブリーチズ(膝丈の半ズボン)  ソックス・・・膝上まであるシルクのロングソックス シューズ・・・小さなリボン付パンプス。 もしくはロングブーツ ダンディの始祖ブランメルの登場により、色はブラック、スタイルはシンプルの一途を辿った男性のオフィシャル・スーツの流行を覆すスタイルだったと言われておる。 また当時スーツの大量生産が可能になった時代であり、生地にもスタイルにも拘りのない庶民も羽織れるお手軽スーツが巷に氾濫したため、ワイルドはそうした風潮に異を唱えるべく、パーツ毎に適度に貴族ファッションの古典的ポイントを取り入れたスタイルを追求したともいわれておる。 こうしたファッション理念が総じて“奇抜”“反抗的”と評されておるのじゃ。 またガッチガチにキメ過ぎて身体の動きに支障をきたすようなお飾りファッションは無用!とばかり、上着やパンツのカッティングや丈にもこだわった。 これは逆に反貴族ファッション的スタイルともいえ、正装着に躍動感を追求した先駆者がワイルドだったとも言えるじゃろう。 なおオスカー・ワイルド的キメ方は、ファッション史においては「小公子スタイル(貴族の子供スタイル)」と命名されとる。 ■ 全米各地でピーピー! キャーキャー!になった、元祖アメリカンズ・アイドル!? ■  ワイルドは生涯に一度アメリカを訪問しとる。 ワイルドの社交界における立ち振る舞いが一部挿入描写された「ペイシェンス」という演劇がアメリカでも人気を博し、興行師がワイルドをアメリカに招待して、70回以上に渡る講演会を開催! 甘く知的なマスク、奇抜ながらダンディの誉れ高いファッション、そして圧倒的な話術とアフォリズムで講演会はどこも大盛況! 女性の黄色い声が会場を彩る!?講演会は、ちょっとしたアイドルのコンサートの様だったらしい。
ワイルドは生涯に一度アメリカを訪問しとる。 ワイルドの社交界における立ち振る舞いが一部挿入描写された「ペイシェンス」という演劇がアメリカでも人気を博し、興行師がワイルドをアメリカに招待して、70回以上に渡る講演会を開催! 甘く知的なマスク、奇抜ながらダンディの誉れ高いファッション、そして圧倒的な話術とアフォリズムで講演会はどこも大盛況! 女性の黄色い声が会場を彩る!?講演会は、ちょっとしたアイドルのコンサートの様だったらしい。この時代のアメリカはまだまだ文化的に未熟な国であり、ヨーロッパのカルチャーを貪欲に取り入れておったが、アメリカン・ガールたちを初めて虜にしたヨーロッパ人のタレントがオスカー・ワイルドだったってことじゃ。 映画というもんはまだ世に存在しておらんし、エルヴィスが登場する約60年前、ビートルズを初めとするブリティッシュ・ロックのインベイジョン(侵略)の70年前の出来事じゃ。 ■ 実は“おホモだち”に夢中じゃった!? ■  初代ダンディのブランメル、2代目オルセイ卿とは違って、同じダンディでもワイルドは本物の芸術家じゃった。 詩人、小説家、演劇作家として大衆にも受け入れられる人気文士じゃった。 しかしそれも30歳半ばまで。 初代ダンディのブランメル、2代目オルセイ卿とは違って、同じダンディでもワイルドは本物の芸術家じゃった。 詩人、小説家、演劇作家として大衆にも受け入れられる人気文士じゃった。 しかしそれも30歳半ばまで。ワイルドの運命を暗転させたのは、多くのダンディが陥るギャンブル狂いによる借金苦、女癖の悪さによる痴情のもつれではなかった。 それは30歳を過ぎて頭をもたげてきた男色志向だったのじゃ。 美少年にいれあげとるうちに、ついに勢い余って某貴族の御曹司とネンゴロになったのが運の尽き。 政界にも顔の効く伯爵の親御さんから訴えられて裁判沙汰となり、ついには有罪となってしもうた。 当時のイギリス社会は同性愛に対して法律の締め付けが厳しくなったばかりであり、ワイルドはその特殊な性癖によって日の当たる世界から完全に抹殺されてしまったのじゃ。 わしは同性愛者の気持ちはまったく分からんが、いろんな文献を読むと、異性との恋愛模様とは決定的な違いがあるようじゃ。 それは同性愛の対象となる人数が少ないだけに、色恋沙汰のトラブルを起こした相手と割りとすぐによりを戻しちゃうことじゃ。 同性愛者として二年間の実刑をうけた後にシャバに出てきたワイルドも、やはりこのパターンに陥ってしまった。 賢夫人の誉れ高かった女房にも今度ばかりはサジを投げられた挙句に先立たれて、執筆依頼も来ない貧窮状態のままでワイルドは亡くなったのじゃ。 やっぱりダンディってのは、スタイルは違っても末路は惨め・・・。 ■ 「芸術活動とは、長く続く自殺行為の様なものだ」 ■  オスカーワイルドの作品の中に「獄中記」ってのがある。 服役中に書かれた随筆集じゃが、次の一節が読者の心を激しく揺さぶる。 オスカーワイルドの作品の中に「獄中記」ってのがある。 服役中に書かれた随筆集じゃが、次の一節が読者の心を激しく揺さぶる。〜悲哀に匹敵する真理はない。 私には悲哀が唯一の真理であると見える時がある。 他のものは、眼あるいは嗜好の幻であり、それは目をくらまし、嗜好を満たすようにされているかも知れない。 しかし、悲哀から数々の世界は作られたのだ。 子供が生まれるにも、星が生じる 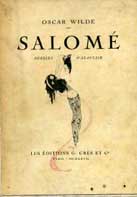 のにも、そこには苦痛がある〜 のにも、そこには苦痛がある〜こんなにも悲しく、美しく、そしてダンディな一節にはそうそうお目にかかることもあるまい。 それでもワイルドは出所後に同じ“罪”を犯して自らの生命を縮めてしもうた。 オスカーワイルド、享年46歳。 ダンディ史上もっとも才気あふれる芸術家だった男を、人は「己の美学に殉じたダンディ」と壮麗に呼んでおる。 しかしわしは「男にも女にも愛されたいという欲望に殉じた男」って呼んだ方が相応しいと思う。 確かにダンディとは極上の“やせ我慢”かもしれんが、やせ我慢と欲望、欲情とは表裏一体じゃ。 どっちがどっちを食いちぎるか、それは神のみぞ知る、じゃ。 ダンディ史上、もっとも人間臭い男、それがオスカー・ワイルドであ〜る! 「ダンディと呼ばれし男たち」の第4回にして、早くも“異端児”を紹介してしもうたが、歴史ってのは同じ様なタイプの者たちの入れ替わり立ち替わりで構築されていくのではない。 エルヴィスあり、ビートルズあり、セックス・ピストルズありのロック・ヒストリーでもお分かりの様に、偉大なる先駆者の功績に対する気高い反抗や新しい解釈の繰り返しによって成立していくのじゃ。 オスカー・ワイルドは、ダンディ史における最初の愛しき反抗者だったのじゃ。 諸君が愛して止まない50sカルチャーにおいてもまた然り。 そいつを未来永劫に存在させるためには、単なる“あの時代”の真空パック、再現だけではなくて、50sカルチャーへの愛と苦悩の果てに生み出される新たなる作品、方法論が必須じゃ。 もう分かるな。 それを実践しておるのがThe-Kingじゃ! もはや芸術じゃよ、芸術! 諸君がおるから、ボスにとって「芸術活動は自殺」にはなるはずもないが、The-Kingのボスにあらたなる生命を与えるべく、迷うことなく大いにお買い物を楽しんじゃおう! ご都合により、お買い物が出来ないなら、オフィスを訪ねて己の50s愛の熱さをボスに伝えよう! それがボスの起爆剤となって、新しいThe-Kingのアイテムの誕生に繋がるのじゃ! |
|
七鉄の酔眼雑記 〜キスマークだらけのお墓 1900年に亡くなったオスカー・ワイルドは、現在フランス・パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されておる。 このコラムでも二、三度紹介したペール・ラシェーズ墓地は、多くの世界的芸術家が埋葬されておることで、パリの代表的な観光名所となっておる。 音楽家ショパン、シャンソン歌手エディット・ピアフ、文豪プルースト、詩人バルザック、更にはドアーズのボーカリストじゃったジム・モリスンらもここに眠っておる。 ジム・モリスンのお墓参りのついで、と言ったら大変失礼じゃが、わしも30年ほど前にオスカー・ワイルドのお墓を訪れたことがある。 右下写真でご覧の通り、ひときわ大きい天使のモニュメントが設置されておるのじゃ。 これはショパンのお墓のシンボルでもあるミューズ(音楽の女神)の像と並んで、ペール・ラシェーズの中でもっとも人目をひく、いわば当墓地のメインプレイスの様相じゃ。 というのも、世界中のワイルド・ファンが途切れることなくここを訪れ、中でも女性ファンはこの天使のモニュメントの唇部分付近にキスマークを付けるのがお墓参りの一種の習わしになっておる! 天使の唇周辺は無数の女性の口紅によってベッタベタになっておった。 いや、中には男性ファンのキスマークもあったんじゃないか? 故人のお墓にキスをするなんぞ、日本人には到底考えられない行為じゃが、オスカー・ワイルドの作品、アフォリズム、生き  様が世界中の文学愛好者の心を捕えて離さないスゴイ証拠であることには違いはない。 まあわしがジム・モリスンの墓碑周辺の敷き砂利をひとつまみ失敬してきたって気持ちと同じなんじゃろうな! 様が世界中の文学愛好者の心を捕えて離さないスゴイ証拠であることには違いはない。 まあわしがジム・モリスンの墓碑周辺の敷き砂利をひとつまみ失敬してきたって気持ちと同じなんじゃろうな!20世紀末期には「ワイルド没後100周年」の機運が高まり、キスマークだらけのモニュメントはきれいに洗浄されて、白いペンキが塗り直されたそうじゃ。 それから10年あまり、今ではまた以前のようにキスマークだらけになっておるんじゃろうか? ダンディとキスマークってのはどうも相容れないと思えるが、真のワイルド・ファンってのは、ワイルドのダンディぶりと同等、それ以上にワイルドの文学作品をこよなく愛しているのだろう。 そいつに関しては、また機会をあらめて紹介するとしよう。 今宵はこれにて! GO TO TOP |