

ROCK 'N' ROLL HOT COLUM by NANATETSU Vol.11
|
| 七鉄「フィフティーズ映画を語る」の巻 「ロック出現」の衝撃を体感できる映画「ジャンボリー」は ロック史を学ぶための貴重な“裏教科書”じゃ! |
 |
ロックンロールが黄金時代に入った1957年に公開された映画「ジャンボリー」。 カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ファッツ・ドミノ、カウントベーシー・オーケストラらの貴重な演奏シーンが拝める映画としてフィフティーズ・ファンにも人気が高いようじゃ。 特にストーリー開始からほどなくして登場するカールのお父さんの演奏シーンは、正面から接写でバッチリ撮られているし、お父さんのお顔の色艶もいいし、演奏もバッチシ。まさに冒頭を飾るといってもいいシーンじゃ。 ジェリー・リー・ルイスもファッツ・ドミノも、期待通り、予想通り、いや伝説の通りの抜群のパフォーマンスをみせてくれる。 ロッカーの登場ばかりに胸をときめかしているファンは、ここまで見せられたら、やっぱりエルヴィスもコクランも見たいとなるだろうが、やっぱり彼らは出演料が高すぎたんじゃろうな。 特にエルヴィスの場合は、パーカー大佐がパイプをくわえて厳しくギャラをチェックするからのお〜。 しかしカールのお父さんの写真がジャケットに無いのはどういうことじゃ、コラア〜。 「ブルー・スウェード・シューズ」のオリジネーターとして脚光を浴びたばかりなのにこの不当な扱いは納得がいかん! でもお父さんはいい人だから、きっと製作側からの気持ち程度のギャラで友情出演してあげたんじゃろうな。 さて、映画のストーリーの方はロックとは全然関係ないんじゃ、これが。 別々に歌手のオーディションにやってきた若い男女。 2人の付き添いでやって来た親同士が、かつての恋人だったっつうところからオハナシはスタート。 一人じゃダメそうだからと、親同士が策を弄して若い息子、娘をデュオに仕立て上げてヒットにこぎつけるんじゃが、ここら辺から大人の醜い算盤勘定が始まるって訳。 やがてデュオは崩壊。 一方だけがソロとして成功していく・・・っつう流れじゃ。 サブタイトルは「ロックンロール大祭り」なんてうたってはいるが、ロックスターはストーリーとはほとんど関係なく、途中で挿入されるCMみたい出てきて、映画の構成上はあくまでもゲストにとどまっておる。 |
|
|
そこで七鉄流、この映画の楽しみ方じゃが、まずロックが登場す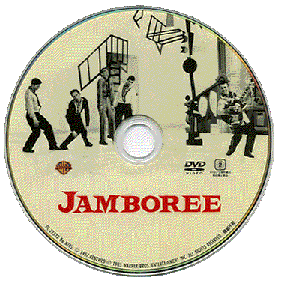 る以前のヒットチャートを独占していた、アメリカン・シュガー・ポップスの実態がよく分かるってもんじゃ。 男は清潔感溢れる好青年、女は汚れをしらない愛くるしい聖少女。 それまでのポップスター像を地でいくキャラで、歌も当然、どこまでも続く青空のようなト・キ・メ・キ・ラブソングじゃ。 る以前のヒットチャートを独占していた、アメリカン・シュガー・ポップスの実態がよく分かるってもんじゃ。 男は清潔感溢れる好青年、女は汚れをしらない愛くるしい聖少女。 それまでのポップスター像を地でいくキャラで、歌も当然、どこまでも続く青空のようなト・キ・メ・キ・ラブソングじゃ。更にスター作りやヒット曲作りの過程、マネージャーのあり方、プロモーションのやり方なども克明に描写されておる。 この時代のスターはレコード会社やマネージャーの完全な操り人形だった訳じゃが、エルヴィスを売り出したスゴ腕マネージャーのパーカー大佐なんかは、研究材料つうか、反面教師として何回も観たんじゃないか、なんてついつい想像してしもうた。 「う〜ん、聴衆に媚びながらスターを作る時代は終わった」とか 「まてよお〜、金を生み出すのはレコードやショーだけではないんと違うか?」とかなんとか呟きながら。 そして旧態然としたポップス界の描写が克明な分だけ、正反対の魅力をもったゲスト出演のロッカーたちの暴れん坊ぶりが強烈じゃ。 ロックファンなら長年見慣れた彼らの姿も、この映画全編を覆うあま〜い50年代の雰囲気の中で見せられると、「だ、誰なんだ、この人は・・・」ってぐらい凄いインパクトがある。 突然出てきたロックンロールってものがいかに常識をひっくり返すような驚くべき存在だったってことが一目瞭然じゃ。 70年代後半に出現したパンクの衝撃度も凄かったけれど、50年代中期のロックンロールの出現に比べりゃガキの屁みたいなもんであり、悪魔、死神、クレイジー、大ばか者、たわけ者、もう世も末じゃ、って大人たちがあらゆる罵詈雑言(ばりぞうごん)でロックンロールを非難したっつうことが今更ながらにうなずけるのお。 確かビートルズのメンバーだったと思うが、「ロックンローラーが出演した50年代の映画では、ロックはまだゴミみたいな扱いだった」と当時を振り返ったことがあった。 しかしこの映画によってロックがはじめて「時代をひっくり返す恐るべき異端児」として“正しい”扱いを受けたことは間違いない。 それほどこの映画の中でロッカーたちは、そら恐ろしいまでに輝いておる。 |
 |
 |
 |
一方ポップスもお好きなお方には、古きよきアメリカン・ポップスの最後の輝きに触れることができるじゃろう。 ポップスとロックンロールの形勢が劇的に逆転する1950年代中期。 昇る朝日のごときロックンロールは輝くばかりじゃが、沈み行く夕陽のごときシュガー・ポップスも儚くもまた美しい。 エルヴィスのブレイクで、カルチャーシーンが嵐の時代を迎えようとしていた時期にあえてこんな映画が封切られたことを考えると、この「ジャンボリー」は音楽シーンの歴史的転換期の実態をとらえた貴重な記録映画ともいうべき存在じゃ。 「衝撃のロックミュージック出現!」をこの映画で実感したわしも、実は心のどこかで愛しのマーガレット嬢と胸ときめくデュオをやってみたかったもんじゃのお〜って、これではロッカーとして失格じゃあ〜。 いい加減マーガレット嬢は諦めて、求むダイナマイト・ガール、ワンダ・ジャクソン姉御といくか! |
|||
★七鉄のアイテム紹介コーナー CATS RING(キャッツリング) KSR-001
 |
 |
ストレイキャッツのデビュー25周年記念としてTHE-KINGから登場したキャッツ・リング。 今回は何とも大胆不敵でハードなエナジーが充満しているこのアイテムに迫ってしんぜよう。 キャッツ・ファンなら既にご存知だろうが、このキャットフェイスのデザインは彼らのデビュー・シングル「RUNAWAY BOY」のシングルにだけ登場する幻のキャラであり、後にモデルチェンジして一気に親しみやすくなったキャラとは正反対の何とも挑戦的な面構えだ。 遠くから見ると鳥が翼を広げているようにも見えるし、至近距離ではどの角度からも見てもエッジが強烈じゃ。 |
| このキャットの面構え、触っただけで火傷しそうなくらい熱いロック・スピリッツが表現されている点では、ロック史上に残る名デザインだ。 こりゃ〜ロック・キャラの定番であるドクロもヘビも爆弾も敵わないとてつもない迫力だわい。 男たる者、こんな顔、表情になる時期は絶対に必要じゃ。 ストレイキャッツがデビューした1981年は、パンクロック最後の黄金期であり、ニューへヴィメタルの黎明期でもある。 要するにハードでへヴィでエネルギッシュなサウンドが時代を謳歌していたのだ。 その中に最小編成バンドで、しかもロカビリー復権という当時としては奇想天外な十字架を背負って登場したストレイキャッツ。 それはまさに命がけのシーンへの殴りこみであり、彼らの決死の覚悟がこのデザインに凝縮されておる。 |
 ストレイキャッツのデヴュー当時のスピリッツをリングという立体で見事に表現してみせたこのアイテム。 このリングの一点撮りをあしらったアルバム・カヴァーがあってもいいぐらいのウルトラ・クールの出来栄えじゃ。 生半可な気持ちじゃ装着できない迫力だが、時には一発勝負でドッガ〜ン!とお洒落をキメてみたい時には最適じゃ。 ストレイキャッツのデヴュー当時のスピリッツをリングという立体で見事に表現してみせたこのアイテム。 このリングの一点撮りをあしらったアルバム・カヴァーがあってもいいぐらいのウルトラ・クールの出来栄えじゃ。 生半可な気持ちじゃ装着できない迫力だが、時には一発勝負でドッガ〜ン!とお洒落をキメてみたい時には最適じゃ。○○の秋〜なんて世間様が優雅に過ごしやすい季節を楽しんでいる時も、男一匹真実一路!ひたすら歩むロック街道!!の精神を貫く諸君に愛用してもらいたいものじゃ! SILVER925, K18 ¥18,900 (税込み) 特注 ALL K18 MODEL ¥155,400 (税込み) |
| 七鉄・雑記編 今年の夏の甲子園は盛り上がったのお〜。 決勝戦に到っては、わしもついつい仕事の手(グラスを持つ手?)を止めて見入ってしまったわい。 病床にある早実OB王貞治ソフトバンク監督も、さぞお喜びになられたであろう。 早実の斉藤君、炎天下の甲子園のマウンドで顔色ひとつ変えず投げ続けるあの脅威のスタミナはあっぱれじゃ。 君こそ、男の中の男じゃ。 わしは密かに、コヤツにスタンディングドラムをやらせたら、すごいプレイをするんじゃないか、なんて突拍子も無いことまで考えておった。 それが一夜明たら「ハンカチ王子」だとお〜? なんじゃそりゃあ〜。 なんでマスコミは世紀の大偉業を成し遂げた男児を、あんな軽薄なノリで報道するんじゃっ! しかもじゃ。 斉藤くんを表紙にした野球雑誌が飛ぶように売れるのはいいとしても、ブルーのハンカチが全国で在庫ギレだとお〜? キレるのはマジわしの方じゃあ〜。 ロッカーの諸君、ま、まさか諸君まで、幸せの黄色いハンカ、いやブルーのハンカチを欲しがっているのではあるまいな? ハンカチっつったら相場は木綿のハンカチーフじゃのうて、その前にブ、ブルースウェードシューズを手に入れんかいっ! いやあ〜わしも大人げないのお〜。 まあハンカチ狂騒曲は今年特有の「真夏の夜の夢」ってことで、今回は周囲のミョウチクリンな騒ぎに惑わされることなく、ロッカー諸君が男として正しい夢を抱き、男らしい戦いができる願いをこめて、若きストレイキャッツのデビュー当時の壮絶な生き様を象徴するアイテム「キャッツリング」をご紹介した訳じゃ。 しかるにい〜、今回ご紹介した「キャッツ・リング」はいいぞっ! これはお洒落品でも、コレクションでも、魔よけでも、戒めでも、夢のシンボルでも、何でもいいから持っていたいオーラがあるっ! 男には拘りぬいた、惚れぬいた逸品はやっぱり必要じゃ。 このリングのキャットフェイスをジャケットにあしらった「RUNAWAYBOY」の頃のストレイキャッツは、20世紀のロックシーン最後のグレイト・エクストラ・クールな面構えだったことを思い出してきた。 男のスタートはかくあるべきじゃ! お盆休みでクールダウンして、珍しくシラフでキメた今回のわしじゃが、ところがどっこい! しっかり飲んどるわい!! そろそろエンジンがかかってきたし、次回はわからんぞっ!!乞うご期待じゃ!! |